
秋葉雄太
2020年入社。土木建築エンジニアリング部にて国内案件を経験した後、2024年からToyo Engineering India Private Limited(Toyo-India)に出張し、設計業務を担当。
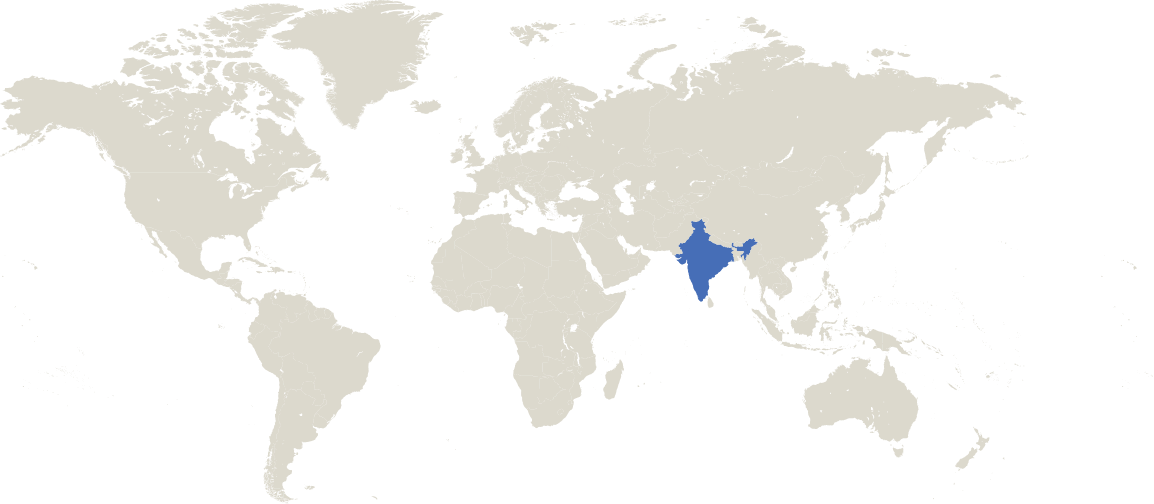
私は土木建築エンジニアリング部に所属し、プラントエンジニアリング全般における土木・建築の設計を行っています。具体的には、タンクやポンプといった各種機器の設置に必要なコンクリート基礎の設計のほか、プラント内の大規模な鉄骨構造物や、オペレーターが働く建屋の設計も手掛けています。
私の役割としては、主に設計に必要な情報を各部署から収集し、スケジュール管理や調整を行うことです。現在携わっている海外エチレンプラント案件では、Toyo Engineering India Private Limited(以下、Toyo-India)が設計作業を担当し、私は各種調整作業や設計図面のレビューや計算結果の確認を行うことが主な業務です。海外の案件ですがお客様は日本の方なので、私がToyo-Indiaとお客様の間に入ってお客様からの要望や設計の思想などの調整などを行います。
今回担当しているのは、海外の某所にある広大な敷地の中に、プラントの設備を建設していく大規模な案件です。当社拠点のToyo-Indiaと協力して進めていて、私は2024年の4月からインドに出張し、約1年間の予定で長期に亘りToyo-Indiaオフィスで勤務しています。
Toyo-Indiaのオフィス全体では約2000人もの従業員がいます。そのうち60人が私と同じ案件で設計を行っていて、そのメンバーを管理するのも私の仕事です。インドのオフィス環境は日本とは大きく異なります。使用言語は英語のみで、大空間に多くのスタッフが集まって働くスタイルを取っています。また、インド人のスタッフは非常に積極的で、活発なディスカッションが日常的に行われています。

入社前は建築学科で主に振動工学を学んでいました。土木建築工学の基本的な知識は、今の仕事にとても活きています。学科以外にも私は「鳥人間サークル」の活動に力を入れていました。飛行機を製作して飛ばすことを目標としたサークルで、設計と製作管理を主に担当し、スケジュールや工程管理を行っていました。
土木建築分野だけでなく配管や機械など多分野と関われるプラントエンジニアリングに興味を持ったのは、サークルで様々な人々と協働する面白さを知ったことがきっかけです。就職活動ではプラント業界に絞り、複数社のインターンシップに参加。その中で、雰囲気が一番自分に合っていると感じたのがTOYOでした。加えて、他社だと専門分野が細かく分かれている印象がありましたが、TOYOでは一人がプラント全体の幅広い業務に携われる点に惹かれ、入社を決意しました。
入社後、最初の3年間で携わったのは国内発電所案件です。プロジェクトの初期段階から参加し、基礎設計図面のレビューに加えて他部署や設計事務所との調整役を担当。その後、現場実習で8カ月ほど工事現場へ赴き、工事業者からの質疑対応や調整業務を任されました。現場では主にトラブル対応や、設計図面に基づく施工方法についての協議などを行いました。
現場ではプロジェクト全体を把握する必要があり、それが私にとって大きな課題でした。また、タイトなスケジュールや狭い敷地での作業など、様々な制約がある中で効率的な施工方法を考える必要がありました。その時に心がけていたのは、疑問点があれば積極的に質問し、自己判断で進めないようにすることです。何か疑問があれば工事現場にいる上司や、オフィスにいる設計部門の上司に相談するなど、疑問を解決しながら仕事を進めていくことを意識しました。
学生時代のサークル経験が仕事に活きているという実感はありますが、規模感は大きく異なります。現場は職人の方も含めると100〜200人規模となり、加えて複数の工事が同時並行で進行しています。3年間の経験を通じて、工事の進行管理や設計プロセスについての理解が深まり、次に何をするべきかという計画立案能力がさらに身についたと思います。

前々から上司には「大規模な案件に携わりたい」と伝えており、2024年に希望が叶い、TOYO-Indiaに長期出張することになりました。初めて海外案件に携わり驚いたのは、国内案件との規模感の違いです。現在の海外エチレンプラント案件では、数百にも及ぶ機器があり、名前から位置まで全てを把握する必要がありました。
設計規準に関しても、それまでの国内のプロジェクトでは日本の規準書を使用していましたが、海外のプロジェクトでは当然英語で書かれた膨大な量の規準書を理解する必要があります。何から手をつければいいのかわからない中、上司からアドバイスをもらいながら必要な情報を見つけ出し、一つ一つ理解を深めていったことが印象に残っています。
また、インド人のスタッフの積極性という部分も、日本とは大きく異なります。例えば、インドの方は「自分はこう思うからこうする」というように、自分の意見をはっきりと主張します。これは日本人とは異なる特徴ですが、相手の考えが明確に伝わってくるため、仕事がしやすい面もあります。
一例ですが、以前、ボルトの設計に関することで、インド人のスタッフと折り合わなかったことがあり、彼らにお客様や他部署と調整した内容を伝えた際、他の方法がいいのではないかという意見が出されました。工数や時間の制約があったため、色々な角度から話し合いを重ね、最終的には折衷案を見出すことができました。
こうした全てのやり取りを英語で行うため、時には困難な状況に直面することもありますが、確実に英語力は鍛えられます。また、日本だとアバウトな指示でも対応してもらえていたことが、海外では正確に伝えないと大きな誤解を招いてしまいます。自分の意図をより明確に伝えるために、きめ細かいコミュニケーションの重要性も同時に学びました。
業務を進める上で苦労は多いですが、自分が携わった設計図面が実際の形になっていく過程を見られることは、私にとってのやりがいです。設計時点では物として見えませんが、2〜3年後に現場を訪れたときや、現場写真を共有してもらったときに、実際に形作られていく様子を目にすることができます。それが自分にとってモチベーションとなり、さらには仕事を続ける原動力になっています。
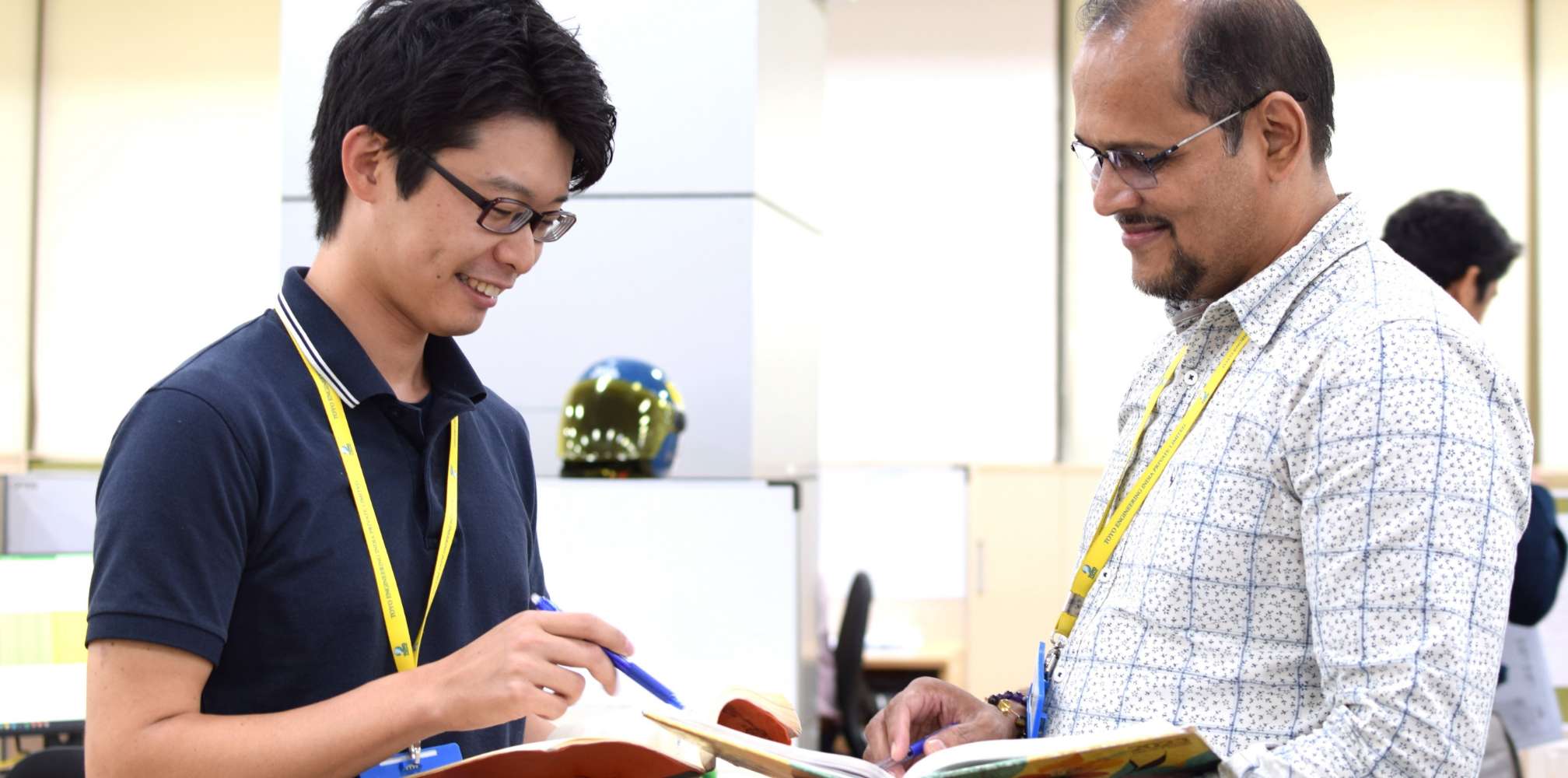
長く海外で生活していると、当然ながら不便に感じることもあります。例えば、ウエットティッシュなどのちょっとした生活用品や缶詰などの日本食材の入手は困難です。しかし、その一方で海外ならではの魅力も豊富にあります。まず、食事面では日本では味わえない本場のインド料理を楽しめます。また、休日は観光に出かけることも多く、日常的に異文化に触れる機会があることも貴重だと感じています。
インドの魅力としては人々の優しさでしょうか。レストランやスーパーでは、店員の方がとても丁寧に接客してくれますし、困っている時には積極的に声をかけてくれます。インドの方はお祭りが好きで、「ディワリ」という大きなお祭りの際には、オフィス内でも飾り付けがされ、そこでは様々な催し物が開かれます。誕生日にはプレゼントを贈り合う習慣もあり、仕事の中にも楽しみを見出し、そこから関係性を築いていくという、日本にはない文化があります。
今後10年の目標は、海外大規模プロジェクトにおける土木建築部門でのリードエンジニアになることです。海外の大規模プロジェクトに、リードエンジニアとして携わりながら、様々な案件を遂行できればと考えています。国内では土地の制限などにより規模に限界がありますが、海外案件ではダイナミックな規模のプロジェクトに携われることに魅力を感じています。
こうした目標達成に向けて、プロジェクト全体の管理や人員の配置、工数管理などのスキルを身につける必要があります。現在は上司の下で、動き方などを実際に見たり聞いたりしながら知識を吸収し、リードエンジニアとして必要なスキルの習得に努めています。一つひとつの経験を大切にしながら、着実にステップアップしていきたいと考えています。


